- Tekst
- Historia
白川郷の黄金伝説 白川郷は合掌造りの村として知られ、世界遺産にも登録さ
白川郷の黄金伝説
白川郷は合掌造りの村として知られ、世界遺産にも登録されている。
合掌造りというのは、掌を合わせたような形の屋根を持つ住まいのことである。この形が完成したのは江戸時代後半(18世紀)で、重い雪でも壊れないように、屋根が下の写真のように造られている。
合掌造りにはくぎが使われていない。屋根の組み立てや修理は、村人が協力し合って行う。現金収入が少ないため、費用をかけずに行わなければならないからである。また、建物の向きは、風や太陽の向きを考えて決められている。風の抵抗を少なくし、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすためてある。
中は広く、2層、3層になっており、上の階では蚕を買い、下では火薬の原料を製造しながら日常生活も送っていた。この辺りは農作物ができないため、江戸時代にこうした家内産業が発展した。合掌造りは白川郷の厳しい自然条件から生まれたものだったのだ。
米がどすれ、年貢が期待できないため、この地を治めようとする者は15世紀前半まではいなかった。しかし、15世紀後半に、ここにやってきて、住み着いた者がいる。
内ヶ嶋為氏とその一族で、白川郷に帰雲城という城を造った。彼らは近くの山で金銀を掘り当て、かなり豊かであったらしい。織田信長などの権力者に金銀を贈ったり、飢きんの時には村人に米を与えたりして、120年のあいだ白川郷を治め続けた。
ところが、1585年11月29日、大地震が起きた。「三百軒以上の家と数百人の人が一人残らず消えた。内ヶ嶋の時代が終わった」と歴史の本に書かれている。
帰雲城がどこにあったのか、これまで何度も発掘が行われているが、まだ見つかっていない。城には金銀が保管してあったはずだ。その価値は今のお金で1兆円とも言われている。白川郷は黄金伝説の地でもあるのだ
白川郷は合掌造りの村として知られ、世界遺産にも登録されている。
合掌造りというのは、掌を合わせたような形の屋根を持つ住まいのことである。この形が完成したのは江戸時代後半(18世紀)で、重い雪でも壊れないように、屋根が下の写真のように造られている。
合掌造りにはくぎが使われていない。屋根の組み立てや修理は、村人が協力し合って行う。現金収入が少ないため、費用をかけずに行わなければならないからである。また、建物の向きは、風や太陽の向きを考えて決められている。風の抵抗を少なくし、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすためてある。
中は広く、2層、3層になっており、上の階では蚕を買い、下では火薬の原料を製造しながら日常生活も送っていた。この辺りは農作物ができないため、江戸時代にこうした家内産業が発展した。合掌造りは白川郷の厳しい自然条件から生まれたものだったのだ。
米がどすれ、年貢が期待できないため、この地を治めようとする者は15世紀前半まではいなかった。しかし、15世紀後半に、ここにやってきて、住み着いた者がいる。
内ヶ嶋為氏とその一族で、白川郷に帰雲城という城を造った。彼らは近くの山で金銀を掘り当て、かなり豊かであったらしい。織田信長などの権力者に金銀を贈ったり、飢きんの時には村人に米を与えたりして、120年のあいだ白川郷を治め続けた。
ところが、1585年11月29日、大地震が起きた。「三百軒以上の家と数百人の人が一人残らず消えた。内ヶ嶋の時代が終わった」と歴史の本に書かれている。
帰雲城がどこにあったのか、これまで何度も発掘が行われているが、まだ見つかっていない。城には金銀が保管してあったはずだ。その価値は今のお金で1兆円とも言われている。白川郷は黄金伝説の地でもあるのだ
0/5000
白川郷の黄金伝説白川郷は合掌造りの村として知られ、世界遺産にも登録されている。合掌造りというのは、掌を合わせたような形の屋根を持つ住まいのことである。この形が完成したのは江戸時代後半 (18世紀) で、重い雪でも壊れないように、屋根が下の写真のように造られている。合掌造りにはくぎが使われていない。屋根の組み立てや修理は、村人が協力し合って行う。現金収入が少ないため、費用をかけずに行わなければならないからである。また、建物の向きは、風や太陽の向きを考えて決められている。風の抵抗を少なくし、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすためてある。中は広く、2層、3層になっており、上の階では蚕を買い、下では火薬の原料を製造しながら日常生活も送っていた。この辺りは農作物ができないため、江戸時代にこうした家内産業が発展した。合掌造りは白川郷の厳しい自然条件から生まれたものだったのだ。米がどすれ、年貢が期待できないため、この地を治めようとする者は15世紀前半まではいなかった。しかし、15世紀後半に、ここにやってきて、住み着いた者がいる。内ヶ嶋為氏とその一族で、白川郷に帰雲城という城を造った。彼らは近くの山で金銀を掘り当て、かなり豊かであったらしい。織田信長などの権力者に金銀を贈ったり、飢きんの時には村人に米を与えたりして、120年のあいだ白川郷を治め続けた。ところが、1585年11月29日、大地震が起きた。「三百軒以上の家と数百人の人が一人残らず消えた。内ヶ嶋の時代が終わった」と歴史の本に書かれている。帰雲城がどこにあったのか、これまで何度も発掘が行われているが、まだ見つかっていない。城には金銀が保管してあったはずだ。その価値は今のお金で1兆円とも言われている。白川郷は黄金伝説の地でもあるのだ
Tłumaczony, proszę czekać..
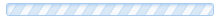
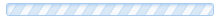
白川郷の黄金伝説白川郷は合掌造りの村として知られ、世界遺産にも登録されている。合掌造りというのは、掌を合わせたような形の屋根を持つ住まいのことである。この形が完成したのは江戸時代後半(18世紀)で、重い雪でも壊れないように、屋根が下の写真のように造られている。合掌造りにはくぎが使われていない。屋根の組み立てや修理は、村人が協力し合って行う。現金収入が少ないため、費用をかけずに行わなければならないからである。また、建物の向きは、風や太陽の向きを考えて決められている。風の抵抗を少なくし、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすためてある。中は広く、2層、3層になっており、上の階では蚕を買い、下では火薬の原料を製造しながら日常生活も送っていた。この辺りは農作物ができないため、江戸時代にこうした家内産業が発展した。合掌造りは白川郷の厳しい自然条件から生まれたものだったのだ。米がどすれ、年貢が期待できないため、この地を治めようとする者は15世紀前半まではいなかった。しかし、15世紀後半に、ここにやってきて、住み着いた者がいる。内ヶ嶋為氏とその一族で、白川郷に帰雲城という城を造った。彼らは近くの山で金銀を掘り当て、かなり豊かであったらしい。織田信長などの権力者に金銀を贈ったり、飢きんの時には村人に米を与えたりして、120年のあいだ白川郷を治め続けた。ところが、1585年11月29日、大地震が起きた。「三百軒以上の家と数百人の人が一人残らず消えた。内ヶ嶋の時代が終わった」と歴史の本に書かれている。帰雲城がどこにあったのか、これまで何度も発掘が行われているが、まだ見つかっていない。城には金銀が保管してあったはずだ。その価値は今のお金で1兆円とも言われている。白川郷は黄金伝説の地でもあるのだ
Tłumaczony, proszę czekać..
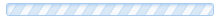
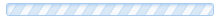
白川郷の黄金伝説白川郷は合掌造りの村として知られ、世界遺産にも登録されている。合掌造りというのは、掌を合わせたような形の屋根を持つ住まいのことである。この形が完成したのは江戸時代後半(18で、重い雪でも壊れないように、屋根が下の写真のように造られている世紀)。合掌造りにはくぎが使われていない。屋根の組み立てや修理は、村人が協力し合って行う。現金収入が少ないため、費用をかけずに行わなければならないからである。また、建物の向きは、風や太陽の向きを考えて決められている。風の抵抗を少なくし、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすためてある。中は広く、2層、3層になっており、上の階では蚕を買い、下では火薬の原料を製造しながら日常生活も送っていた。この辺りは農作物ができないため、江戸時代にこうした家内産業が発展した。合掌造りは白川郷の厳しい自然条件から生まれたものだったのだ。米がどすれ、年貢が期待できないため、この地を治めようとする者は15世紀前半まではいなかった。しかし、15世紀後半に、ここにやってきて、住み着いた者がいる。内ヶ嶋為氏とその一族で、白川郷に帰雲城という城を造った。彼らは近くの山で金銀を掘り当て、かなり豊かであったらしい。織田信長などの権力者に金銀を贈ったり、飢きんの時には村人に米を与えたりして、120年のあいだ白川郷を治め続けた。天正13年(1585年)11ところが、年月29日、大地震が起きた。「三百軒以上の家と数百人の人が一人残らず消えた。内ヶ嶋の時代が終わった」と歴史の本に書かれている。帰雲城がどこにあったのか、これまで何度も発掘が行われているが、まだ見つかっていない。城には金銀が保管してあったはずだ。その価値は今のお金で1白川郷は黄金伝説の地でもあるのだ兆円とも言われている。
Tłumaczony, proszę czekać..
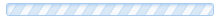
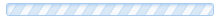
Inne języki
Tłumaczenie narzędzie wsparcia: Klingoński, Wykryj język, afrikaans, albański, amharski, angielski, arabski, azerski, baskijski, bengalski, białoruski, birmański, bośniacki, bułgarski, cebuański, chiński, chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, cziczewa, duński, esperanto, estoński, filipiński, fiński, francuski, fryzyjski, galicyjski, grecki, gruziński, gudżarati, hausa, hawajski, hebrajski, hindi, hiszpański, hmong, igbo, indonezyjski, irlandzki, islandzki, japoński, jawajski, jidysz, joruba, kannada, kataloński, kazachski, khmerski, kirgiski, koreański, korsykański, kreolski (Haiti), kurdyjski, laotański, litewski, luksemburski, macedoński, malajalam, malajski, malgaski, maltański, maori, marathi, mongolski, nepalski, niderlandzki, niemiecki, norweski, orija, ormiański, paszto, pendżabski, perski, polski, portugalski, rosyjski, ruanda-rundi, rumuński, samoański, serbski, shona, sindhi, somalijski, sotho, suahili, sundajski, syngaleski, szkocki gaelicki, szwedzki, słowacki, słoweński, tadżycki, tajski, tamilski, tatarski, telugu, turecki, turkmeński, ujgurski, ukraiński, urdu, uzbecki, walijski, wietnamski, węgierski, włoski, xhosa, zulu, łaciński, łotewski, Tłumaczenie na język.
- colitis chronica gradus minoris probabil
- In the end we only regret the chances we
- Cupidas homines coecos facit
- What is your first memory of coming to G
- When you will not be interested
- Ale sie rozpisalam !!
- kolpomyoperineoplastica
- Czekam jutro na wiadomosc
- Latyczyn ac aliarum in Pallatinatu Belze
- pellarum
- Cupiditas homines coecos facit
- Odezwiesz sie jeszcze ?
- Phasis inactiva
- Intralobulare
- beatissima pellarum es
- najbardziej bolesna
- jest ryzyko jest zabawa
- miliaris
- Dobranoc
- Neoplasma malignum probabiliter carcinom
- dla wiernych i czystych rąk
- friends check checked love
- Jestes najwazniejsza osoba w moim zyciu
- Liphonodualitis reactiva

